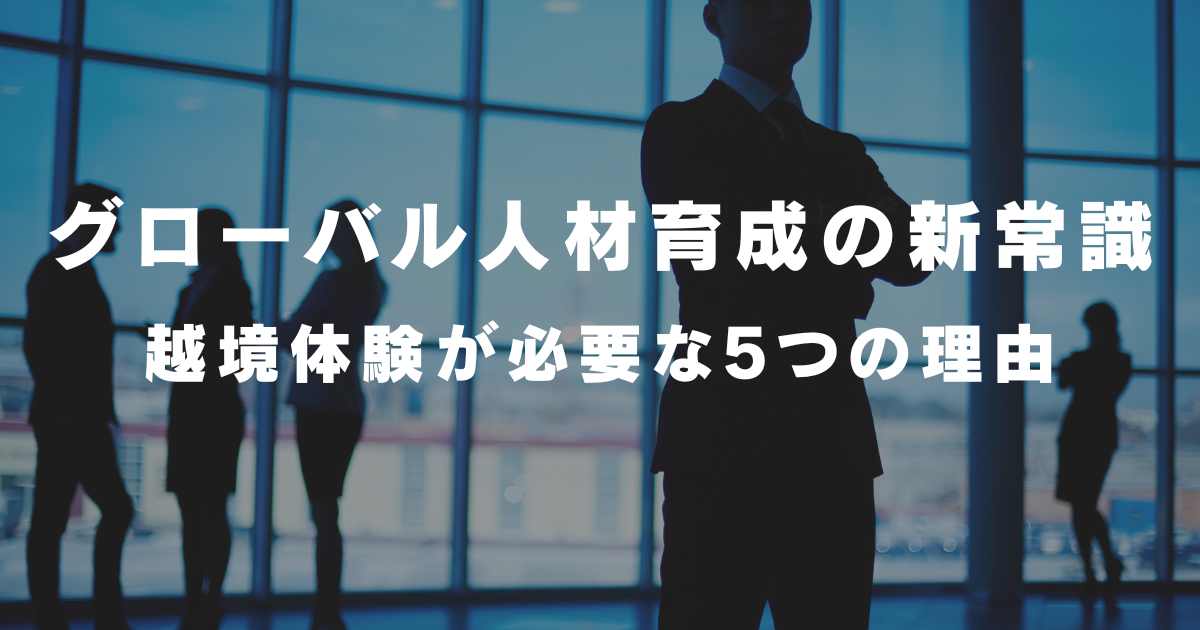なぜ「今」、グローバル人材育成が企業にとって不可欠なのか?
「グローバル人材=英語力」だと思っていませんか?
確かに語学力は必要です。しかし、それだけでは、変化の激しい国際社会で本当に活躍できる人材は育ちません。今、企業に求められているのは、“自ら動ける”人材──すなわち、常識の通じない環境でも、答えのない問いに挑み、自ら道を切り開いていける変革の担い手です。
本記事では、なぜ今、日本企業にとってグローバル人材育成が不可欠なのかを明らかにし、その本質が「越境体験」にあることを5つの理由と企業事例を通して解説します。語学力や座学にとどまらない、本質的な人材育成のあり方を再考していきましょう。
【時代背景】国際競争と国内市場の変化が育成の前提を変えた
いま、日本企業が本気でグローバル人材育成に取り組まなければならない理由は明確です。国際競争の激化、国内市場の縮小、テクノロジーの急速な進化──これらすべてが、従来の延長線上にある人材戦略ではもはや立ち行かないことを示しています。
【現場のリアル】グローバル市場では「正解のない問い」が日常化している
グローバル市場では、既存の成功モデルや常識が通用しない場面が日常的に訪れます。変化のスピードが速く、文化や価値観が多様で、どのような解決策が通用するかは現場で自ら見極めるしかありません。こうした「正解のない環境」において、指示待ちではなく、自ら課題を見つけ、解決へ導ける“探索型”人材こそが求められているのです。
【働き方の変化】リモート化が進み「越境コラボ」が日常に
さらに、テレワークやオンライン会議の浸透により、国境を越えたチーム連携やプロジェクト推進は日常的になりました。異なる文化圏との協働においては、「語学力」以上に、相手を理解しようとする好奇心、価値観の違いを乗り越える対話力、そして柔軟な適応力が問われます。
【育成の限界】座学では育たない「探索力・共創力・自己変容力」
タイガーモブが注目するのは、そうした力を座学や社内研修だけで育むのは難しい、という現実です。実際に、常識が通じない“本番環境”に身を置いたとき、人は初めて自己の思考パターンや行動スタイルに向き合い、変革のきっかけを掴むのです。
グローバル人材育成は、変革のプロセスそのもの
つまり、グローバル人材育成とは、単に英語を学ぶことではありません。未知の環境に飛び込み、価値観を揺さぶられ、思考の枠を超えて成長していくプロセスそのものです。VUCA時代の今だからこそ、日本企業は本質的な「人材の育て方」を見直す必要があります。
「語学力」では足りない──グローバル人材に本当に必要な資質とは
【語学力の限界】英語力は“スタートライン”に過ぎない
多くの企業がグローバル人材を語る際に、まず挙げるのが「語学力」です。確かに、共通言語としての英語が話せることは重要です。しかし、それは“スタートライン”に過ぎません。語学力だけでは、文化や価値観の異なる人々と信頼関係を築き、共に成果を上げることはできません。
【必要資質①】“未知への好奇心”が異文化理解の原動力になる
グローバル人材に求められるのは、「異なる価値観や行動様式を前提とした環境」で成果を出す力です。まず必要なのが、“未知への好奇心”です。例えば、タイガーモブが実施する海外越境プログラムでは、誰もが慣れ親しんだ環境を離れ、アウエイな環境で、常識が通じない場に身を置きます。
そんな状況で成果を出すには、「なぜこの人はこう考えるのか?」と、相手を理解しようとする姿勢が欠かせません。違いを否定するのではなく、理解し共に進む「共創力」が問われるのです。
【必要資質②】“自己内省力”が変化への柔軟性を育てる
次に挙げられるのが、“自己内省力”です。文化が違えば、正解も違います。そんな中で自らの行動や思考を振り返り、柔軟に修正できるかどうか。これは、正解のない課題に挑み続ける上で、極めて重要な力となります。
【必要資質③】“変革創造人材”が未来を切り拓く
タイガーモブが重視する「変革創造人材」とは、決められた目標をこなすのではなく、自ら問いを立て、道を切り開いていく人材です。この資質は、上司の指示に従うことに慣れた環境では育ちにくく、混沌とした“本番環境”でこそ芽吹くものです。
語学力だけではない、本質的な資質を育てる視点へ
語学力だけではなく、未知に飛び込み、相手と対話し、自らを問い直しながら前に進む力──それが、これからのグローバルビジネスを牽引する人材に本当に必要な資質です。
なぜ“越境体験”がグローバル人材育成に不可欠なのか?
【理由①】変化の激しい時代において、自走できる人材が求められている
今、企業が育てるべき人材像は、指示待ちで動くオペレーターではなく、「自ら課題を見つけ、自ら動ける人材」です。テクノロジーの進化、グローバル競争、そして予測不能な社会変化が次々に訪れるVUCA時代──そんな環境で成果を出すには、従来のマニュアル通りの行動では通用しません。
越境体験は、そうした「自走力」を開花させるのに最適な場です。日々、異文化の中で「何をすべきか」「どう動くか」を自ら判断し続けることが求められ、自然と自律性と意思決定力が鍛えられていきます。
【理由②】語学力だけでは通用しない、複雑な環境下での共創力が必要
多くの企業は「英語ができればグローバル人材」と考えがちですが、現実はそう単純ではありません。異文化環境では、語学よりも重要なのは「なぜそのように考えるのか?」と相手の背景に興味を持ち、違いを受け入れて共に成果を出す力──すなわち“共創力”です。
タイガーモブのプログラムでは、多国籍のスタートアップや社会起業家たちと協働する場が用意されています。そこでは、自分の意見を押し通すのではなく、異なる価値観と対話しながら前に進む実践力が育まれます。
【理由③】本番環境でしか得られない「内面からの変容」が成長の鍵
社内研修やOJTでは、安全圏から出ることは難しく、思考も行動も“慣れ”の中にとどまりがちです。ところが、海外という未知の現場に身を置くと、自分の前提が通じない瞬間が訪れます。文化も、仕事の進め方も、求められるスタンスもまったく違うのです。
このような“異質との衝突”こそが、自己の内面を揺さぶり、価値観の変容を引き起こします。単なるスキルではなく、ものの見方そのものが変わる──それが本質的な人材育成の第一歩です。
【理由④】“予定調和”では育たない、正解のない問いに挑む力が身につく
多くの日本企業の研修は、「決められた課題に対し、決められた解を出す」ことを求めます。しかしグローバルビジネスの現場は違います。課題そのものが曖昧で、何をゴールとすべきかも自分で定義しなければなりません。
越境体験では、「そもそも何が課題なのか?」「なぜそれが起きているのか?」と問いを立てる力が養われます。この“問いの力”は、イノベーションや新規事業開発の場面で不可欠な能力であり、まさに企業の未来を担う人材に求められる要素です。
【理由⑤】価値観を揺さぶられ、自分の軸を見直すことでリーダーシップが育つ
グローバルに活躍する人材に必要なのは、周囲に流されない「自分の軸」です。しかし、その軸は座学で築けるものではなく、むしろ多様な環境に揉まれる中で、自ら見出すものです。
越境体験を通じて、自分が大切にしている価値観や働く意味が何かを徹底的に問われます。ときに挫折や衝突を経験しながらも、そこから逃げずに向き合うことで、自分だけのリーダーシップのスタイルが育ちます。これは、次世代リーダー育成における最も重要な成果のひとつです。
実践が人を変える──グローバル人材育成の企業事例3選
「本当にそんなに変わるのか?」
そう思った方こそ、ぜひ以下の企業事例をご覧ください。タイガーモブの越境型研修を導入した企業では、参加者本人だけでなく、受け入れた組織全体にポジティブな変化が波及しています。
【事例①】ANAフーズ株式会社:Webマーケと営業改革で売上120%達成
研修形式:ベトナム現地フルコミット型(3ヶ月)
対象者:TOEIC730点超の若手営業社員
実施内容:
- タンソンニャット空港での新規営業開拓
- 既存顧客売り場の改善による売上アップ
- Instagram・Facebook活用によるプロモーション戦略の構築
成果と変化:
「与えられた仕事」ではなく「自分で創る仕事」に挑んだことで、当人の主体性が大きく変化。「ミッションを自分で定めて達成する」というスタンスが、帰国後の業務にも活きており、役員層からも高評価を得た。
【事例②】カルビー株式会社:現地1,350名との協働でビジネス感覚が覚醒
研修形式:カンボジア現地派遣(1年間)
対象者:総務4年目の若手社員
実施内容:
- スイーツコーナーの立ち上げ
- 現地スタッフとの倉庫・店舗業務改善
- 日本食輸入体制の仕組み化
成果と変化:
現地での“リアルな泥臭さ”を体感する中で、「正解のない現場で考え抜く力」が鍛えられた。計画だけでなく“実装”の重要性を理解し、データでは見えない現場の声を起点としたPDCAを回せる人材へと進化。
【事例③】株式会社NTTデータ:開発人材が経営視点を得て社内提言へ
研修形式:オンライン越境プログラム(3ヶ月)
対象者:システム開発6年目のプロジェクトリーダー
実施内容:
- 現地スタートアップとのプロジェクトマネジメント
- コーポレート業務全体の課題整理と改善提案
- 英語での業務報告・意思決定支援
成果と変化:
「これまでは上司のミッションを達成することが仕事だった。でも今は、自分で課題を定め、会社の方向性まで見据えて行動している」──これは、研修後の本人の言葉である。越境体験を通じて得た“自分の軸”が、チームや組織に変革の波をもたらしている。
これらの事例は、どれも「越境」という挑戦を経たことで、人が大きく“覚醒”することを示しています。短期間でも、環境と視点が変われば、人材は驚くほど変わるのです。
育成を“仕組み化”する──越境体験を成功に導く企業側の体制とは
越境型のグローバル人材育成は、個人にとって劇的な成長をもたらします。しかし、その成長を一過性で終わらせず、組織全体の力に転化するためには、「企業側の仕組み」が不可欠です。
【1】人事と現場の連携による“ゴールの共有”
まず重要なのは、人材を送り出す目的を明確にすることです。「なぜこの社員を派遣するのか」「研修の成果をどう活かすのか」を、本人・上司・人事が三者で共有することで、育成体験が本人だけの“思い出”で終わることを防げます。
タイガーモブでは、出発前のマインドセット研修を通じて、この「内発的動機の明確化」を重視しています。
【2】成果の“見える化”と社内への還元プロセス
研修後、本人の成長や学びを社内に還元する仕組みも必要です。タイガーモブの導入企業では、以下のような取り組みが成果を挙げています:
- 中間報告会:越境体験の途中経過を上司や人事にプレゼン
- 最終報告会:成長の証を可視化し、社内ナレッジとして蓄積
- 振り返りシートの共有:週次で気づきを文書化し、行動の変容を定点観測
これにより、研修後も本人の行動変容が持続しやすくなり、周囲の巻き込みもスムーズになります。
【3】越境後の配置とキャリア設計
研修の効果を組織的に最大化するには、越境体験後の配置も重要です。帰国後に従来通りの業務に戻してしまうと、せっかくの成長が活かされず、本人のモチベーションも下がってしまいます。
実際、成功している企業では以下のような配慮をしています:
- 新規事業や海外部門へのアサイン
- 育成担当や後輩指導のポジションで経験を伝承
- 社内イノベーションプロジェクトへの参画
育成とキャリア開発をセットで捉えることが、真の意味での「グローバルリーダー創出」につながります。
【4】外部パートナーとの連携
最後に、実践型の越境プログラムを設計・運営するには、高い専門性が求められます。送り出す企業にとって、危機管理、研修設計、現地との調整を一手に担うパートナーの存在は不可欠です。
タイガーモブは、世界40カ国以上のパートナー企業との連携実績を持ち、マッチングから事前研修、事後支援までを一貫して提供。企業が安心して人材を送り出せる体制を構築しています。
グローバル人材の育成は、個人任せではなく“組織の戦略”として捉えるべき時代に入りました。越境体験という「非連続な学び」を、企業の持続的な成長につなげるために──今こそ、人材開発のあり方を再構築するタイミングです。
越境体験こそ、グローバル人材育成の本質
VUCA時代、そしてグローバル競争が激化する今、企業が求めるべき人材像は明らかに変わりつつあります。ただ英語が話せるだけでは不十分。異なる価値観の中で考え、動き、共創し、変化の中で成長し続ける──そんな「探索型人材」が、企業の未来を切り拓くカギを握ります。
そしてその力は、決して座学や研修室の中だけでは育ちません。常識の通じない“本番環境”に身を投じ、自ら問いを立て、壁を越えていく越境体験こそが、人材を覚醒させ、変革の担い手へと押し上げるのです。
この記事で紹介した5つの理由と、実際の企業事例が示すように、越境体験は「一部の選抜人材」だけでなく、今後は「すべての社員に必要な学び」となっていくでしょう。
もし、御社が次の一手としてグローバル人材育成を本気で考えるなら──
まずは「越境から始まる学び」を導入してみてはいかがでしょうか。
変化の激しい時代において、人材育成は最大の投資であり、最大の競争力です。未来を担う人材の可能性を信じ、彼らに“本物の挑戦”の場を提供すること。それが、組織全体の進化を加速させる第一歩となるはずです。