【教育現場で注目】探究学習とつながる「海外修学旅行」導入事例に学ぶ成功のポイント
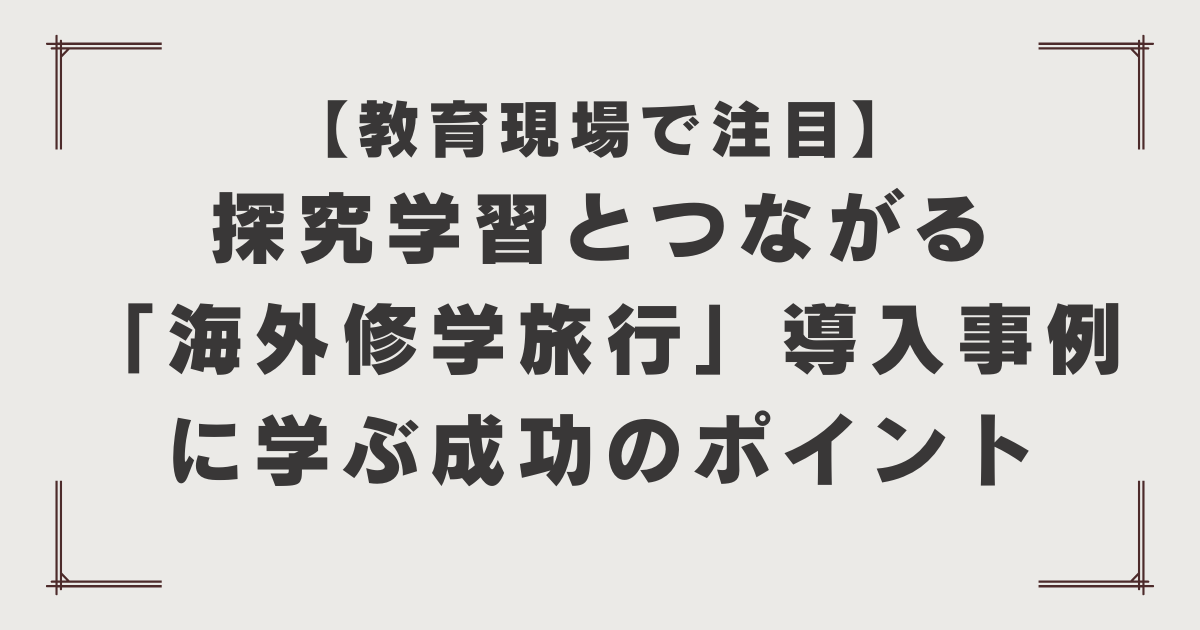
「修学旅行の在り方を、時代に合わせて見直したい」
こうした声が、今、全国の中学校・高等学校で高まっています。
従来の修学旅行といえば、名所旧跡を巡る観光や、学年全体での集団行動が中心でした。しかし近年、探究学習やグローバル人材育成の重要性が叫ばれる中で、単なる「体験」にとどまらず、**実社会との接点を持つ“学びの旅”**として、海外修学旅行が注目を集めています。
特に、**「Learning by Doing(実践を通じた学び)」**の考え方を取り入れた海外派遣プログラムは、生徒の非認知能力を育む新たな手法として、教育機関や自治体で導入が進んでいます。実際に、アジアやアフリカのスタートアップ企業を訪問し、地域課題の解決に挑む中学生・高校生の姿が増えつつあります。
とはいえ、いざ導入を検討するとなると、
- どんなプログラムがあるのか?
- 安全面や費用はどうか?
- 本当に教育効果はあるのか?
- 他校や他自治体はどうしているのか?
といった具体的な情報を必要とされる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「修学旅行 海外」というテーマで検索される教育関係者や自治体担当者の方々に向けて、国内外で導入された先進事例や、生徒にどのような変化が起こったのか、教育的効果や運営体制の実際までを詳しくご紹介します。
探究学習とグローバル体験を融合させた新しい修学旅行が、どのように生徒の成長を支え、教育現場に新たな選択肢をもたらしているのか。具体的な事例とともに、わかりやすくご紹介します。
なぜ今、修学旅行に「海外」を取り入れるのか?
グローバル化、探究学習、非認知能力の育成…。従来の観光型修学旅行から脱却し、未来の教育を担う海外体験型の修学旅行が注目されています。教育現場が今、海外に目を向ける理由を解説します。
1. 修学旅行の「学び」が問われる時代にけ身の体験に終始してしまう――
生徒の主体性を引き出せない構造
従来の修学旅行は、主に「思い出づくり」や「団体行動の訓練」といった側面が強く、学習効果は二次的な位置づけでした。しかし、2020年度からの新学習指導要領により、**主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)**が全教科で求められるようになったことに伴い、修学旅行の目的そのものが再定義されつつあります。
特に中高生の成長段階において、「自ら問いを立て、探究し、社会とつながる体験」は、記憶に残るだけでなく、将来の進路やキャリア形成にまで影響を与える重要な学びの契機となります。そのため、修学旅行もただの観光ではなく、「学びの場」としての再設計が求められているのです。
2. 「探究的な学び」と「越境体験」の親和性
探究学習は、課題を自分で見つけ、情報を集め、仮説を立て、検証するプロセスを重視します。国内でもこの形式は可能ですが、異文化環境での実践(越境体験)は、その効果を何倍にも高める土壌になります。
たとえば、現地の社会課題に触れたり、スタートアップの経営者と対話したりする経験は、日本では得難い“リアルな問い”に直面する機会を生みます。「なぜこの国ではプラスチックごみが増えているのか?」「地域の水不足にどう対応しているのか?」といった問いは、実体験の中で自ら生まれるものであり、教室では得られない学習の深まりが期待されます。
3. 国・自治体による制度と取り組みの広がり──教育旅行の再定義が進む背景とは?
国際理解やグローバル人材育成を重視する動きは、学校現場にとどまりません。文部科学省の施策に加え、地方自治体が独自に海外派遣事業や助成制度を展開する例も増えています。
たとえば、文科省が推進する「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構想」では、探究学習の一環として国際的な課題に取り組むプログラムが数多く採択され、企業や大学との連携、海外での活動が組み込まれています。
一方、自治体レベルでは、教育委員会に限らず、青少年育成や国際交流を担当する部署が中心となり、地域の中高生を海外に派遣する取り組みが全国的に広がっています。人口減少や地域経済の縮小に直面するなか、“外の世界”とつながる教育機会の提供が、将来を担う世代への重要な投資として認識されてきているのです。
また、自治体でも青少年育成や地域のグローバル化を目的に、独自の海外派遣事業や助成制度を設ける動きが広がっています。社会的背景として、単なる観光から“教育としての修学旅行”への転換が加速しており、海外体験の導入はその中核に位置づけられつつあります。
このように、修学旅行を「学びの場」へと転換する動きは、国や自治体の制度と連動して進んでいるのが現状です。教育機関単独では実現が難しい部分を、制度的・財政的に支援する体制が整いつつあります。
修学旅行で海外へ行くと何ができる?
プログラム内容と教育効果の全体像
単なる語学研修ではない、実社会と接続した「学びの設計」が海外修学旅行の魅力。プログラムの種類や実施方法、導入しやすさについて具体的に紹介します。
「Learning by Doing」による学習デザインとは?
従来の修学旅行では、訪問地での観光や施設見学を中心に、学習との接続が限定的でした。これに対し、**実社会の課題と向き合いながら学ぶ「Learning by Doing(実践を通じた学び)」**の考え方を取り入れた海外修学旅行では、訪問そのものが「探究活動」となります。
たとえば、海外のスタートアップ企業と連携し、「現地の社会課題に対して、どう解決策を提案できるか」といったテーマに取り組むことで、課題発見・情報収集・仮説構築・プレゼンテーションといったプロセスを、生徒が自然な形で体験できます。
このような設計は、生徒の思考力・表現力・協働力といった非認知能力の育成に直結し、「ただの修学旅行」で終わらせない深い学びを生み出します。
現地渡航型とオンライン型、それぞれの特徴
海外修学旅行には大きく分けて現地渡航型とオンライン型の2種類があります。
● 現地渡航型:
現地の人々との対話、街の空気、文化の違いを五感で体験できるのが最大の特長です。英語などの言語を実際に使いながら活動するため、**生徒の内発的動機づけ(やる気)**にもつながります。一方で、費用・期間・安全管理などの準備が求められます。
● オンライン型:
移動の制約なく、海外と接続した学びを実現できるのが強みです。スタートアップの経営者や社会起業家とのセッション、バーチャル視察、プロジェクト型課題解決などを通じて、実社会のダイナミズムを教室に持ち込むことができます。コロナ禍を機に導入が広がり、現在も継続的な実施が可能です。
それぞれの形式にはメリット・制約がありますが、学校の予算や学年ごとの目的に応じて最適な形を選択できる柔軟性があることが、導入しやすさにもつながっています。
事前研修・事後研修まで一貫設計された学びのプロセス
海外修学旅行が「点」で終わらず、「線」としての学習に昇華するためには、事前・事後の学習設計が欠かせません。
① 事前研修では、派遣先の地域課題や文化背景を調べ、生徒自身が「なぜこのテーマに取り組むのか」「何を知りたいのか」といった目的意識を形成します。
②「現地またはオンラインでの実践」を経て、
③ 事後研修では、経験を振り返り、グループでの共有や個人レポートを通じて「自分にとっての意味」を言語化していきます。
この一連のプロセスは、教育的観点からも極めて重要です。**探究の循環プロセス(課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現)**に合致するため、単位認定を行う高校も増えてきています。
海外修学旅行が「点」で終わらず、「線」としての学習に昇華するためには、事前・事後の学習設計が欠かせません。
- 事前研修では、派遣先の地域課題や文化背景を調べ、生徒自身が「なぜこのテーマに取り組むのか」「何を知りたいのか」といった目的意識を形成します。
- 現地またはオンラインでの実践を経て、
- 事後研修では、経験を振り返り、グループでの共有や個人レポートを通じて「自分にとっての意味」を言語化していきます。
この一連のプロセスは、教育的観点からも極めて重要です。**探究の循環プロセス(課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現)**に合致するため、単位認定を行う高校も増えてきています。
導入した学校・自治体では何が起きた?
海外修学旅行の実例とその成果
実際に海外修学旅行を導入した学校や自治体の事例から、その効果と成果を紹介します。学習成果だけでなく、非認知能力の育成、価値観の変容といった本質的な変化にも注目します。
【導入事例①】修羅場体験から得た主体性と課題発見力(ANAフーズ)
企業研修として活用されたケースの一つに、ANAフーズの若手社員が東南アジアの現地企業と共同プロジェクトに取り組んだ事例があります。渡航先では、準備不足や言語の壁、現地パートナーとのミスコミュニケーションなど、「想定外のトラブル」が次々と発生。しかしその“修羅場”こそが、参加者にとって最大の学びの機会となりました。
対応策を自ら考え、現地メンバーと協力しながら状況を打開したことで、参加者は「自分が行動しなければ何も進まない」という強い主体性と課題発見力を身につけたといいます。
このような体験は、生徒にとっても大いに応用可能です。与えられた問題ではなく、自ら課題を発見し、解決に動く行動力を促す点で、探究学習の実践にも直結します。
【導入事例②】異文化環境での実践でマネジメント力を育む(カルビー)
カルビーでは、管理職候補を対象とした海外研修プログラムを実施。現地のスタートアップ企業にチームで入り込み、業務支援と課題解決に取り組みました。
プロジェクトを成功に導くには、限られた時間内で他者と信頼関係を築き、合意形成を図りながら行動する必要があります。この中で参加者は、異文化環境においても柔軟に対応し、チームをマネジメントする力を磨きました。
中高生にとっても、こうした実践型の活動を通じて、リーダーシップや対人関係能力を育成することが可能です。生徒が年齢に応じた難易度でプロジェクトに参加する設計を行えば、学校教育にも十分応用できます。
【導入事例③】チームで働く経験から生まれる自己理解と協働性(NTTデータ)
NTTデータでは、若手社員が多様な国籍のチームメンバーと協力し、現地で新規事業のアイデアを提案するというプログラムを実施しました。
参加者の多くが口にしたのは、「自分が得意だと思っていたことが通用しなかった」「一方で、他者との違いを活かすことでチームが前進した」という気づきです。これは単なるスキル習得ではなく、自己理解と他者理解、そして協働の価値を学ぶ機会となりました。
同様の体験は、探究型の修学旅行にも応用可能です。学年やクラスを超えたチーム編成や、現地の若者との協働を取り入れることで、生徒一人ひとりの役割意識や協調性を高めることができます。
【担当者の声】役員や保護者が納得した「変化の証」
導入を決定する際に重要なのが、「保護者や学校内の理解を得られるかどうか」です。
ある教育機関では、事前にプログラム内容を教職員と保護者に丁寧に共有し、実施後には生徒の振り返り発表会を開催。参加した保護者や教員からは、「これまでにないほど自信を持って話す姿に驚いた」「“変わった”ことがはっきり伝わってきた」との声が寄せられました。
つまり、教育的効果が可視化されることで、関係者全体の理解と納得が得られやすくなるのです。
「越境型学び」はなぜ中高教育に効果的なのか?
探究型教育との親和性を解説
企業で成果を上げている「越境型プログラム」が、なぜ中高教育機関にも有効なのか。その背景と理由を論理的に解説します。実際に導入する際に知っておきたいポイントも、あわせてご紹介します。
越境のインパクトは年齢が若いほど大きい
教育心理学や発達段階の観点から見ても、中高生は自己形成期の真っただ中にあり、「自分とは何か」「社会とは何か」を模索する過程にあります。この時期に異文化や社会課題に直面する経験は、視野を広げるだけでなく、価値観やアイデンティティ形成に深く影響することが数多くの研究で指摘されています。
また、固定観念が形成されきっていない若年層ほど、「越境」による価値観の揺さぶりが柔軟に受け入れられやすく、その後の学びや行動に与える影響も大きくなります。つまり、海外体験による“変化”の種を最も深く根づかせることができるタイミングが、中高時代なのです。
学校の「探究学習」課題と一致する育成目標
探究学習の導入が進む中で、多くの学校が直面するのが「形式だけの探究になってしまう」という課題です。問いを立てても、それが机上の調査に終わってしまい、生徒の本質的な変容にはつながりにくいという声もあります。
海外修学旅行での越境体験は、こうした探究学習の課題を補完します。現地での課題探究は、「答えのない問い」と向き合う実践そのものであり、生徒は情報の不確実さや異文化との摩擦の中で、思考を深めていきます。
つまり、海外体験を含む探究活動は、「知識」ではなく「認識の変化」を促す学びであり、学習指導要領が掲げる「主体的・対話的で深い学び」の体現に最適な手段のひとつです。
「導入のしやすさ」と「汎用性」の両立
実践型の教育プログラムは、とかく「一部の先進校しかできない」「高コストで一般化が難しい」と思われがちです。しかし、近年では民間事業者の支援や補助制度の活用により、予算規模や学年構成に応じた柔軟な設計が可能となっています。
また、海外修学旅行プログラムは、学年全体で実施するタイプから、希望者制、部活動や特別活動と連携した少人数実施まで、多様な形に適用できる汎用性も持ち合わせています。
この柔軟性こそが、中高教育機関における導入のハードルを下げ、**“特別な学校だけのもの”ではなく“多くの学校に開かれた選択肢”**として受け入れられる大きな要因です。
タイガーモブの海外修学旅行が選ばれる3つの理由
──他社との違いとは?
教育機関、自治体、企業の皆様へ多数の導入実績を持つタイガーモブ社の「海外修学旅行」プログラム。その選ばれる理由を、設計思想・実施体制・費用対効果の3点から整理します。
教育機関向けの豊富な実績と支援体制
タイガーモブは、もともと企業向けのグローバル研修を強みとする教育系スタートアップとして誕生しました。そこで培ったノウハウを活かし、学校向けに特化した海外修学旅行プログラムを提供しています。
中高生の発達段階や教育目標に即したプログラム設計はもちろん、探究学習との連携や事前・事後学習の教材提供、振り返りワークショップの実施など、学校現場の実情に即したサポート体制が整っているのが特長です。
これまでに導入された学校・自治体では、「準備段階から実施後の報告まで安心して任せられた」という声も多く、教育関係者にとって信頼性の高いパートナーとして位置づけられています。
1名からでも対応できる柔軟性とコーディネート力
従来の海外修学旅行は「学年全体で実施」「数十名以上が前提」といった制約があり、少人数での導入が難しいケースもありました。
タイガーモブのプログラムでは、1名からの個別参加にも対応しており、他校合同での派遣、学年横断型での実施、部活動単位での企画など、学校ごとの事情や希望に柔軟に対応可能です。
また、現地の受け入れ先となるスタートアップやNPOとのネットワークを活用し、参加目的や学習テーマに応じて最適なマッチングを行うコーディネート力も大きな強みです。これにより、「生徒にとって意味のある海外体験」が実現しやすくなります。
経済産業省認定、補助金対象事業としての信頼性
タイガーモブの教育プログラムは、経済産業省「越境的学習プログラム」のモデル事業に加え、2025年度には「探究・校務改革支援補助金」の支援事業者にも採択されており、教育的効果や社会的意義が公的に評価されています。
また、一部の自治体では、海外派遣に対する助成金制度の対象として認定されているケースもあり、費用面の不安を軽減できる可能性があります。こうした制度活用についても、導入時に丁寧なサポートを受けられる体制が整っています。
特に2025年度は、経済産業省「探究・校務改革支援補助金2025」の支援事業者として正式に採択されました。これにより、小中高校や自治体が同社の探究型グローバルプログラム「WORLD CAREER CARAVAN」を費用負担なしで導入できる仕組みが整備された実績もあります。
信頼性の高い事業者と連携することは、保護者や教育委員会との調整を進めるうえでも大きな安心材料となるでしょう。
導入までの流れとよくある疑問
──現場の不安に寄り添ったサポートとは?
「導入の流れは?」「どの学年で実施すべき?」「安全管理は?」など、よくある質問に丁寧に答えながら、導入までの不安を払拭します。
導入までのステップをわかりやすく解説
海外修学旅行の導入は、通常の行事とは異なる調整や準備が必要です。以下のようなステップで進めることで、スムーズな実施が可能になります。
実施・事後学習
本番の実施後は、成果の振り返りや発表を通じて、学びを定着させます。報告会や記録資料の共有により、校内外の関係者にも成果を可視化することが可能です。
目的設定・校内合意形成
まずは「なぜこのプログラムを導入するのか」を明確にし、教職員間での合意形成を図ります。探究学習との接続や学校の育成方針と照らし合わせながら、教育的意義を整理することが重要です。
事業者との相談・企画設計
タイガーモブのような実績ある事業者と連携し、対象学年、人数、テーマ、予算などに応じたプランを検討。現地派遣型・オンライン型など形式に応じた調整もこの段階で行います。
保護者説明・安全確認
保護者への説明会を実施し、教育的価値や安全対策、費用負担の有無などを丁寧に説明します。信頼できる実施体制や補助制度の存在は、保護者の理解促進にもつながります。
教職員・保護者の理解を得るためのポイント
導入時に最も多く寄せられる懸念のひとつが「関係者の理解が得られるかどうか」です。とくに海外派遣となると、安全面や費用負担への不安が大きくなります。
こうした不安に対応するためには、以下の工夫が有効です。
- 探究学習や育成目標とつなげた明確な目的提示
- 過去の導入事例を交えた説明会の実施
- 信頼できるパートナーとの連携体制の提示
- 補助金などの活用による費用面の工夫
「どんな変化が期待できるか」「どのように安全管理をしているか」など、具体的なエビデンスや実績を示すことが理解促進のカギとなります。
予算・スケジュールの見立てと工夫
予算やスケジュールの面でも、柔軟な設計が求められます。たとえば以下のような方法で調整が可能です。
- 補助金制度の活用:前述の通り、探究補助金や自治体の助成制度を活用することで費用負担を抑えられるケースがあります。
- 学年横断型・希望制の活用:1学年全体ではなく、希望者制や他学年合同での実施により、規模やコストの調整が可能です。
- 年度内での分散実施:長期休暇を活用した小規模分割実施など、学校行事との調整も柔軟に対応できます。
このように、「やりたいが現実的に難しい」という声にも応えられる柔軟な設計と支援体制が整っていることは、導入を検討する教育機関にとって大きな安心材料となります。
\今すぐチェック!/実際に導入した学校・自治体はどうだった?
導入事例をまとめた資料を無料プレゼント中!
実際に海外研修を導入した教育機関や自治体のリアルな事例を、資料にまとめました。どんな地域・学校で、どんなテーマや方法で実施されたのか、参考になる情報が満載です。海外派遣や探究学習の導入を検討中の方は、まずは事例からヒントを見つけてみませんか?
全国の中高・自治体の多彩な実例を掲載
本事例集には、国内外の研修先で実施された多様なプログラムの実例を収録しています。アジアや欧州への派遣型、オンライン型、地域の課題と結びつけたテーマ型など、実施形式や目的に応じた柔軟な設計が分かる構成です。
各事例には、実施背景や研修内容だけでなく、事前・事後の学習プロセスや、生徒の変容、保護者・教員の声なども収録されており、検討材料として非常に実践的な内容となっています。
ダウンロード方法と資料請求の流れ
事例集は、専用フォームから無料でダウンロードいただけます。
ご請求後、登録アドレスに資料を即時送付いたします。今後の導入検討や校内協議、保護者説明の際の資料としてもご活用いただけます。
まとめ:未来をつくる世代に、“越境体験”という選択肢を
グローバル化が進み、探究学習や非認知能力の育成が重視される今、修学旅行や海外派遣といった学びの機会にも、より深い教育的意義が求められる時代になりました。
単なる観光や視察にとどまらず、**若者が異なる社会と出会い、自ら考え、行動する「越境体験」**が、注目を集めています。
こうした取り組みは、学校現場における探究学習の一環としてはもちろん、自治体が主導する青少年育成・国際交流事業としても高い価値を発揮しています。生徒・若者にとって、社会とつながるリアルな経験は、自身の将来を考える大きなきっかけとなり、地域全体にも新たな視点をもたらします。
すでに多くの教育機関・自治体で導入が進み、その効果や工夫が共有されつつあります。もし、「導入に向けて何から始めるべきか迷っている」「他の地域・学校の事例を参考にしたい」とお考えであれば、まずは無料の事例集をご活用ください。
学校規模でも、自治体主導でも、地域の文脈に合わせた設計が可能です。探究学習、青少年の育成、国際交流──そのすべてをつなぐ次世代型の海外体験が、いま多くの関係者から注目を集めています。
未来をつくる世代に、いま越境の機会を。
皆さまの検討やご相談を心よりお待ちしています。
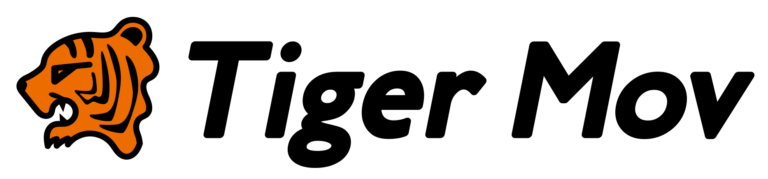
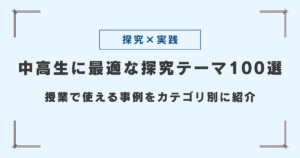
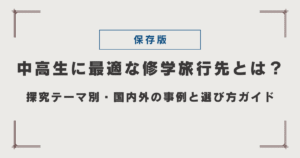
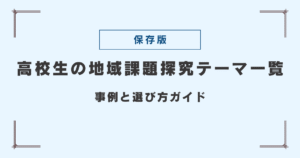
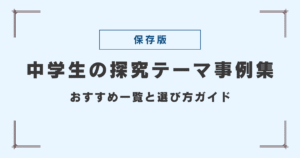
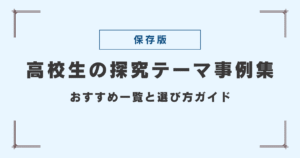
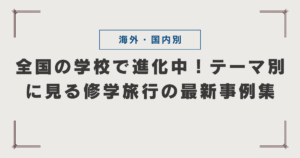
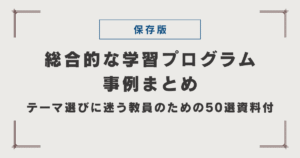
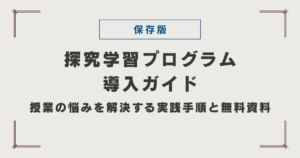
コメント