【事例紹介】探究学習と連動した高校修学旅行の企画事例|国内外で学びを深める実践型研修とは?
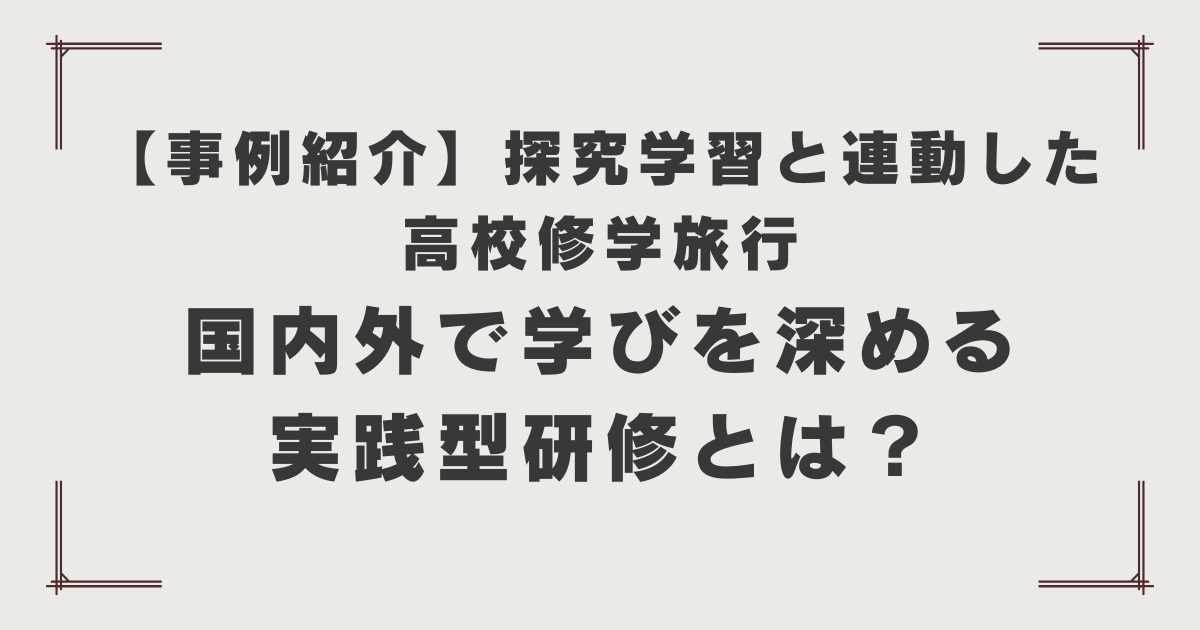
探究的な学びと修学旅行が融合する時代に
これまでの修学旅行は「観光を通じた体験」に重きが置かれてきました。しかし近年、探究学習の重視を背景に、その役割が見直されています。
2022年度から始まった新学習指導要領では、「総合的な探究の時間」を軸に、生徒が社会と接続しながら学ぶことが求められています。その実践の場として注目されているのが、学校外での「越境体験」を取り入れた修学旅行です。
探究学習においては、正解のない問いに挑む力や、主体性・協働性・内省力の育成が重視されます。これを支える場として、日常を離れたリアルな環境での学びが効果を発揮します。
実際に、地域資源を活かした国内研修や、グローバル課題に取り組む海外研修など、既に多くの学校や自治体が修学旅行を「学びの旅」へと転換しつつあります。
本記事では、そうした探究型の修学旅行の最新事例を紹介し、企画・導入を検討される教員の方々に向けて、実践のヒントをご提供します。
教育機関・自治体が選ぶ、探究型研修の設計ポイント
探究型修学旅行を実施するうえで重要なのは、「何を学ばせるか」だけでなく、「どう学ばせるか」です。タイガーモブが支援するプログラムの設計には、いくつかの共通する教育的視点があります。それは、①越境体験、②内省の時間、③実践への接続という3つの軸です。
まず、「越境体験」は、生徒が日常の環境から一歩外へ出ることで、新たな視点や価値観と出会う機会を指します。これは地理的な越境(国内外の移動)だけでなく、文化・社会課題・他者との関係性といった、認知的な越境も含みます。
次に重要なのが「内省の時間」です。生徒が自らの体験を振り返り、意味づけすることで、学びが一過性の経験にとどまらず、自己認識や行動変容へとつながります。タイガーモブのプログラムでは、ファシリテーターによる対話や振り返りワークを通じて、この内省を支援します。
また、「実践への接続」も大きな特徴です。単なる見学や体験で終わらせず、生徒が自らの問いを立て、現地での観察やヒアリングを通じて答えを探るプロジェクト設計が取り入れられています。これは、探究学習の目的である「問いに基づく学び」を修学旅行という枠の中で実現する仕掛けです。
さらに、こうした学びを支えるには、事前・事後の学習設計も不可欠です。例えば事前には、研修先の社会課題や文化背景について調査したり、自らの問いを立てたりする時間が設けられます。一方で事後には、研修の成果をポスターやプレゼンで発表することで、学びを言語化し、他者と共有するフェーズが用意されています。
最後に、タイガーモブのプログラムは完全カスタマイズ型で、学校の教育方針や対象学年、実施時期に応じて柔軟に設計されています。これにより、各校の特色に合わせた“意味ある学びの旅”が可能になります。
国内での探究型研修事例(自治体導入)
探究学習と連動した修学旅行や校外研修は、すでにいくつかの自治体や教育委員会において先進的な取り組みが行われています。
探究的な学びを実現する場として、修学旅行や校外研修の再設計に取り組むのは高等学校だけではありません。自治体主導で継続的に実施されている海外研修プログラムも、青少年育成を目的とした公共性と教育的信頼性の高いモデルとして注目されています。
こうした自治体の取り組みは、学校単独での実践とは異なるスケールや設計思想を持ち、地域社会と一体となった教育のあり方を体現するものです。また、同じ国を訪問先としながらも、自治体によってテーマやアプローチが大きく異なる点は、一つの渡航先でも多様な教育的価値を引き出せることを示しています。
これらの事例は、高校が研修を設計するうえでもヒントが豊富です。たとえば、地域と連携して継続的に学びの機会を提供する仕組みや、教育テーマを社会全体の課題と接続する方法など、学内での探究を社会とつなげる発想の転換を促すヒントが詰まっています。
ここでは、自治体主導で海外研修を実施した2つの事例を紹介します。
福岡県直方市|起業家教育としてのフィンランド派遣
「総合的な探究の時間」を導入する際、多くの高校現場が共通して直面する課題があります。特に指導に関わる教員にとっ福岡県直方市では、地域として「起業家教育の推進」を掲げ、中学生・高校生を対象に海外派遣プログラムを実施しています。訪問先はフィンランド。教育先進国として知られるこの国で、現地のスタートアップ支援機関や教育機関との交流を通じて、生徒たちは「働くこと」や「自分の将来」に関する視野を広げました。
本プログラムは教育委員会が主導し、地元の中高生が一緒に渡航する点が特徴です。特に印象的なのは、単なる訪問や体験にとどまらず、「問いを持って現地に向かう」ことを重視していた点です。事前学習では、起業やキャリアに関するリサーチを行い、渡航後にはそれぞれのテーマに対するインタビューやフィールド調査を実施。事後には報告会形式で成果を共有し、地域での発信にもつなげられています。
この取り組みは、地域の教育ビジョンと連動しながら、探究と越境学習の好事例として注目されています。
東京都品川区|Well-beingを探究する越境体験
一方、東京都品川区の公立中学生を対象としたフィンランド研修は、「Well-being(幸福な生き方)」をテーマに据えたプログラムです。こちらも教育委員会主導の事業であり、「生徒一人ひとりが自分にとっての幸せを考え、言語化すること」を目的に設計されました。
プログラムの特色は、フィンランドの教育現場だけでなく、現地で暮らす人々との対話を通じて、生徒が異なる価値観に触れる設計にあります。幸福度の高い国として知られるフィンランドにおいて、「なぜ人々が幸せなのか」を自分の視点で探ることが主眼です。
また、本研修では心理的安全性を確保した学習環境も重視されており、現地での学びを安心して言語化・共有できるようファシリテーションが組み込まれていました。探究の入口として「幸福」という概念を扱うことで、生徒自身の自己理解や他者理解が深まるよう配慮されています。
高校主導による海外研修の成功事例
自治体主導の研修に加え、学校単独で独自の海外研修を企画・実施する事例も増えています。ここでは、教育方針に探究を据えた高校による実践的な事例を紹介します。
田園調布学園|「BOTTO PROJECT」での自分探究と海外研修(バリ)
田園調布学園では、高校2年生を対象に「BOTTO PROJECT(Be Original, Think, Try, Own)」と名づけた探究プログラムを実施しています。このプログラムは1年間にわたり、「自分らしい幸せとは何か」という問いを軸に、自分自身を深く掘り下げるプロセスを踏みます。
その一環として行われたのが、インドネシア・バリ島での海外研修です。生徒たちは、自らの問いに関連するテーマを設定し、現地の社会起業家やNPOと協働しながらフィールド調査を実施。例えば「教育格差」「女性の就労」などの社会課題について、現地の実情を知り、自らの価値観を問い直す体験を重ねました。
帰国後には、探究の成果をプレゼンテーションやポスターにまとめ、全校で共有。研修は単発の経験に終わらず、学内での対話と振り返りを通じて、自己理解と社会的関心の深化につながっています。
5校合同研修|社会課題と向き合うアジア研修(インド/バリ)
複数校の生徒が合同で参加する形式の研修も注目されています。2023年度には、5校から集まった高校生がインドとバリを訪れ、それぞれの地域が抱える社会課題をテーマに探究を行いました。
このプログラムでは、事前にオンラインで顔合わせやテーマ設定を行い、現地ではチームごとに課題解決型のフィールドワークを実施。インドではスラム支援に取り組むNGO、バリでは循環型社会を目指す地域団体と連携し、生徒はインタビューやワークショップを通じて多角的に課題と向き合いました。
異なる学校から集まった生徒たちが協働し、共通の問いに挑むことで、対話力・多様性理解・協働的問題解決力が自然と育まれる設計がされています。
ドルトン東京学園|4ヵ国を横断した年間型探究プログラム
ドルトン東京学園では、1年間を通して複数国に渡航する「グローバル探究プログラム」を設けています。生徒はフィリピン・バリ・韓国・日本国内で、持続可能性や文化理解をテーマに探究を進めます。
特徴的なのは、海外での学びと国内での振り返りを交互に繰り返す「往還型設計」です。現地での体験を内省し、次の研修につなげることで、学びが連続的に深まっていきます。加えて、生徒は自分自身の問いを軸にリサーチを行い、研修の最終段階では学校内外に向けて成果発表を行います。
こうしたプログラムを通じて、生徒は主体的に学びを設計し、複数の視点を行き来しながら、より深い自己探究と社会接続を経験しています。
公募型プログラムによる柔軟な学びの形
探究型の研修を学校単位で企画・運営するには、時間や予算、人員配置といった面で課題がつきものです。そうした中で、個人参加型の公募型プログラムが、より柔軟で実効性のある選択肢として注目を集めています。
タイガーモブが展開する「タイガーモブスクール」は、全国の中高生を対象とした海外・国内の研修プログラムです。各地域の社会課題や文化的背景をテーマに設計されており、生徒は希望制で参加し、同世代の仲間とともに越境体験に挑みます。学校では得がたい学びや刺激を得られる点が、大きな特長です。
たとえば、バリでは「環境×起業」、ザンビアでは「教育と多文化共生」、ネパールでは「農村開発とジェンダー」といったテーマのもと、地域密着型の研修が行われています。いずれも現地の当事者と直接対話し、自分の問いを掘り下げる設計がなされており、探究的な学びに深く根ざしています。
これらの公募型プログラムは、個人だけでなく学校単位での導入も可能です。たとえば「数名の生徒を選抜して派遣し、学校内で事前学習や事後発表を実施する」といった連携型の運用により、比較的少ない負担で本格的な探究体験を実現できます。
「個人の挑戦」から「学校の変化」へつなげる学び
加えて、現地では経験豊富なファシリテーターが常に伴走し、生徒の不安を和らげながら、学びを支える環境が整えられています。「やりっぱなし」に終わることなく、内省と振り返りの時間を重視した構成が、生徒の気づきを深め、学びを定着させます。
実際、参加後の生徒には明確な変容が見られます。保護者や教員からは「自分の考えを言語化する力がついた」「将来への視野が広がった」といった声が寄せられ、学校全体の探究活動への関心や意欲を高める効果も生まれています。
このように、公募型プログラムは、生徒個人の関心に応じた挑戦の場であると同時に、学校の教育活動全体に波及する可能性を秘めた取り組みです。今後、より多くの学校が柔軟に取り入れていくことで、探究の学びはさらに広がっていくでしょう。
高校修学旅行の企画に役立つ導入フロー
探究学習と連動した修学旅行を設計する際、従来の観光型とは異なる観点が求められます。ここでは、探究型研修の導入を検討する高校が、どのようなステップで企画を進めればよいのか、具体的な導入フローを紹介します。
1. 目的の明確化:「なぜ実施するのか」を問い直す
まず重要なのは、「修学旅行で何を学ばせたいのか」という目的の言語化です。これは行き先やスケジュールよりも前に検討すべき根幹です。
たとえば、「自己理解を深める」「社会課題への関心を育てる」「異文化を通じて価値観の多様性を体感する」など、探究的な視点から教育的目的を明確にすることで、その後のプログラム設計に一貫性が生まれます。
2. 教育課程との接続:「探究の時間」とどう連動させるか
修学旅行が一過性のイベントで終わらないよう、総合的な探究の時間や教科と接続することが重要です。
たとえば、事前学習で「問いの設定」や「リサーチスキル」の育成を行い、研修後には「発表」「振り返り」「論文化」などのアウトプットにつなげる設計が求められます。学内での横断的な連携や評価設計の工夫もポイントです。
3. パートナー選定:教育的視点を共有できる事業者か?
訪問先や現地活動の設計において、外部パートナーとの連携は不可欠です。その際、観光中心の旅行会社ではなく、教育目的に対応できる実績のある事業者を選定することが望まれます。
研修設計の段階から「問いを持って行く設計」「内省の時間配分」「心理的安全性の確保」などを共有できるパートナーは、学びの質を大きく左右します
4. 参加生徒の選抜と支援:全員参加型 or 志願制
探究型研修は内容が深いため、生徒の関心や準備状況に応じた参加設計も重要です。たとえば、全学年を対象とする場合は内容の基礎化、志願制の場合は選抜やフォローアップ体制の構築が求められます。
また、家庭の経済状況によって参加を諦めることがないよう、奨学金や助成制度の検討も教育的公平性の観点から重要です。
5. 研修後の展開:学びを学校内に還元する仕掛け
探究型研修は内容が深いため、生徒の関心や準備状況に応じた参加設計も重要です。たとえば、全学年を対象とする場合は内容の基礎化、志願制の場合は選抜やフォローアップ体制の構築が求められます。
また、家庭の経済状況によって参加を諦めることがないよう、奨学金や助成制度の検討も教育的公平性の観点から重要です。
研修は、帰国して終わりではありません。むしろ、そこで得た気づきをいかに学校全体に還元するかが、企画全体の価値を左右します。
発表会・ポスターセッション・校内展示・動画編集・学校広報への活用など、参加者だけでなく、周囲の生徒・教員・保護者にも波及するような展開が理想です。
このように、探究型修学旅行の導入には「教育的視点からの設計」「事前事後の学習設計」「外部との連携」が欠かせません。一つひとつの要素に丁寧に取り組むことで、生徒にとっても教員にとっても、学びの深い機会となるはずです。
まとめ:探究学習を深めるための修学旅行・研修設計とは
修学旅行や校外研修を「探究の場」として再定義する動きは、全国の高校で加速しています。その背景には、変化の激しい社会を生きる生徒たちにとって、知識だけでなく「自ら問いを立て、他者と協働しながら深く学ぶ力」が求められていることがあります。
本記事では、自治体による取り組み、高校主導の先進事例、公募型プログラムといった多様なアプローチをご紹介しました。いずれの実践にも共通していたのは、以下の3つの視点です。
- 越境体験:異なる価値観や文化と出会うことで、自分の枠を超える学びが生まれる
- 内省と対話:ただ経験するだけでなく、自分の言葉で振り返る時間が学びを深める
- 社会との接続:探究テーマが現実社会とつながることで、主体的な関心と行動が芽生える
こうした要素を取り入れた研修は、単なる「旅行」ではなく、教育活動の一環として生徒の成長を支える強力な機会となります。
現在、多くの学校が新たな学びの形を模索する中で、他校や他地域の実践事例を知ることは、企画の精度を高める大きな助けになります。
私たちは、今回ご紹介した事例も含めた「海外・国内研修事例集」やサービス紹介の資料3点セットをご用意しています。探究学習の観点から企画設計された事例を、テーマ別・形式別にご紹介しており、貴校の企画にすぐに役立つ内容です。
ぜひ以下より資料をご請求いただき、自校での探究型修学旅行・研修設計にお役立てください。
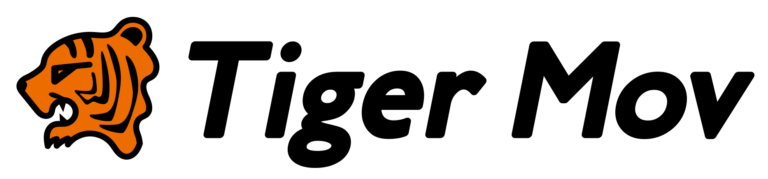
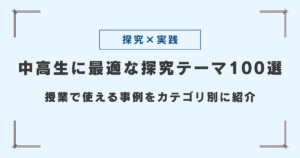
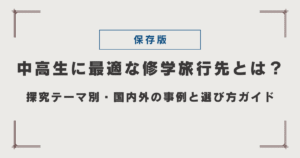
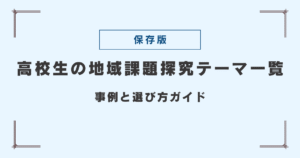
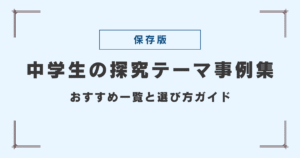
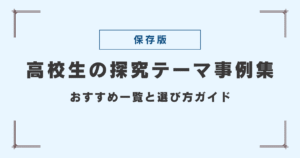
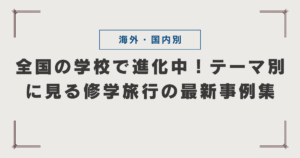
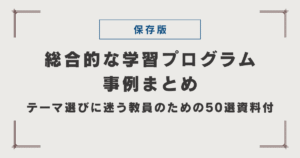
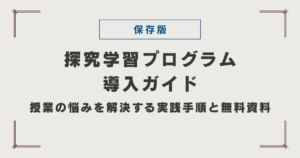
コメント